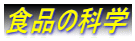�H�i�̕ۑ��Z�p
�@���Â̐́A�l�ނ͍r����삯���A�G�߂̖̎�����̂�A���⏬�������A�������Ď��������̐��v�𗧂āA�H�Ƃ�ǂ��Ĉړ����Đ������Ă����ƍl������B�������A�V��s���Œ��J����������A���Ƃ�̔N����������A�L���E�L�삾�����肵�āA�H�i���ԕۑ�����K�v�ɔ���ꂽ�B�����́A�������ĐH�ׂ���Ȃ����⋛��V���Ɋ����Ċ��������������̂悤�ł���B�����炨�悻13,000�N�O�̐Ί펞����A�l�ނ͉��g�����Ƃ��o���A���H������M�E�������s���悤�ɂȂ�A�X��������o�鉌�ɂ���Ċ���(����)���邱�ƂŁA�H�ނ̒����ۑ����\�ɂȂ����B���ꂪ�ۑ��Z�p�̎n�܂�ƍl������B
���H�i���H�ƕۑ���
�H�i���H�Ƃ́A�P�ɐH�i�����H���邱�Ƃ����ł͂Ȃ��A�����̎���A�q���Ǘ��A�H���Ǘ��A�E�ہE�ۑ��A�Ⓚ�Z�p�A��Z�p�܂Ŕ��ɕ��L���Z�p�̏W���ł���B
�H�i�́A�H�ׂ��l�̖��ɗ����̂łȂ���Ȃ�܂���B���̂��߂ɂ́A�H�i�̈��S���iSafety�A���������܂߂��L�Q�������܂܂Ȃ����Ɓj�ƕۑ����iSoundness�A���ς��Ȃ����Ɓj���m�ۂ��邱�Ƃ��K�{�����ƂȂ�B
�H�i���H�H��ɂ�����H�i�̕ۑ���������l�����ɉ����āA�悸�H�i���ۑ��ł��Ȃ�������˂��~�߁A�@���ɂ��Ă��̌�������菜�������͉���E�܂��͔�����x�������邩���d�v�ł���B
�H�i�ϔs�̎�ȗv��
�@�@�@��@���@���@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
��ȗv��
|
���s �F(���ρA�ΕρA�ސF�c) ����(�d���c) �ɂ���(���������A���L��) ��(�ꂢ�A�_���ς��c) �e�N�X�`���[(�ڂ��ڂ��A�l�o�l�o) �h�{�f�j��iV.C�c�j ���̑� |
|
|
|
�@ |
�����w�I�v�� �E�������I�v�� �E�y�f�I�v�� �E�����I�v�� ���w�I�v�� �����I�v�� |
|
|
|
||
�T�D�����w�I�ȗv��
�E�������I�v��
�@�@�Y�Ƃւ̗��p�F���A�݂��A�ݖ��A�p���A�N�T���A�Ђ����A�[���A���[�O���g�A�`�[�Y�A�L�����A���߂Ȃ�
�@�@�i���̗F�@��ʐ��ہA�a�����ۓ��ɋN�����镅�s�A�ϔs�A���y�E�c���A�J�r�̔����Ȃ�
�E�y�f�I�v��
�Y�Ƃւ̗��p�F���ނ̐����A�����������A�����h�~�A�ő�����Ȃ�
�i���̗F�@�J�X�^�[�h�N���[���̋�ݔ����A�[���[�̓�A�}�C�^�P���蒃�q�����̖��Ì�
�E�����w�I�v��
�@�@�Y�Ƃւ̉��p�F�o�i�i�A�L�E�C�Ȃǂ̒Ǐn(EO�K�X�Ȃ�)
�U�D���w�����ɗv��
�@��ʂɁA�d���E�_���E�����ɋN������
�E�|���t�F�m�[���̕ϐF
�@�@�@�S�C�I���ɂ��^���j���̕ϐF
�@�@�@�|���t�F�m�[���ɂ�����
�@�@�@�N�����t�B���̕ϐF
�E���ƃA�~�m�_(�A�~�m�J���{�j������)
�E�����̎_��
�E���̑�
�V�D�����I�ȗv��
�Љ��A�V���A�ʼn��A��A�S�x�ቺ�A�����A�z���A�j��ȂǐH�i�̎����Ă��镨��(���I���W�[)�r���ɂ��ώ��⍁��̔�U�ɂ��ώ�
�E �f���v���̌Љ��ƘV��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �~�Z���\���̕ω�
�E �H�i���̐����ړ��A���萬���̔�U
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����Z�p�ɂ��ۑ�������