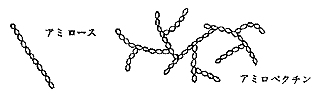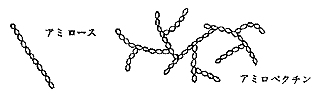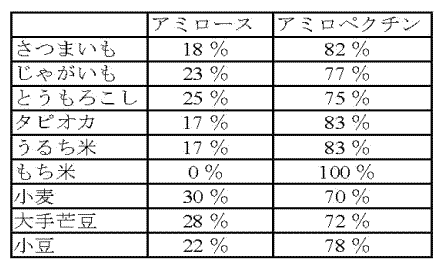3.物理的要因
糊化、老化、固化、軟化、粘度低下、乾燥、吸湿、破壊など食品の持っている物性(レオロジー)喪失による変質や香りの飛散による変質
・ デンプンの糊化と老化
ミセル構造の変化
・ 食品中の水分移動、香り成分の飛散
→包装技術による保存性向上
1.デンプンの糊化と老化
デンプンとは
デンプンはブドウ糖がつながった物質で、つながり方により、1直線につながったアミロースと、枝分かれしたアミロペクチンの2つの物質で構成されている。
アミロ一スとアミロペクチンの構造
各種デンプン中のアミロースとアミロペクチン含量
糊化とは何か
・デンプンに水を加えて加熱すると、ミセル構造がほぐれ、膨潤し、全体が均一なコロイド状物質になる。これを糊化(α化)というが、糊化したデンプンは、粘性をもち、もとのデンプンと著しく性質が異なっている。α化したデンプンを常温で放置すると次第に水に不溶性となる。これは、デンプンが部分的に天然澱粉の状態に戻った現象で、β化または老化という。御飯や餅をつくったり、パンを焼いたりクッキーに仕上げるのは、原料中のデンプンをα化して美味しく食べられるようにするためで、古くなったパンや冷飯がボソボソしてまずいのは元のβデンプンに戻ったからである。
・アミロ ースが多い米は、ぱさぱさの飯に、少ないと粘りのある飯になる。餅米のような、アミロペクチンを多く含む米は、分岐があるためミセル化しにくいので老化が起こりにくい。
・デンプンを利用した調理食品は老化によりシェルフライフ(貯蔵生命)を失うので老化しにくいデンプンが望まれるが、逆に葛きり、はるさめ等は老化する性質を応用した食品である。
・糊化温度はアミロペクチンの方が高く、糊化した溶液の粘性もアミロペクチンが大で、溶液の濃度が高くなるほどアミロースとの差は大きくなる。
|
|
| |
粳米 |
小麦 |
とうもろこし |
馬鈴薯 |
甘藷 |
タピオカ |
| 糊化温度(℃) |
70〜80 |
62〜83 |
65〜76 |
55〜65 |
58〜67 |
64〜79 |
|
老化に関する因子
1.温度 : 60℃以上の高温では老化は起こり難く、凍結させない限り低温ほど老化を起こしやすい。 2〜5℃で老化が最も速やかである。
2.水分 : 水分が10〜15%以下の乾燥状態では老化は起こらない。水分が30〜60%で最も老化しやすく、水分が多くなると再び老化が遅くなる
3.pH : pH13以上のアルカリ性では老化が起こり難い。pH4付近で、老化が抑制される。pH6〜7付近では、急速に老化が進む
4.分子構造 : 直鎖状分子のアミロースの水溶液は中性、または酸性で非常に不安定で老化しやすい事から分子の直鎖状部分が長いほど老化を起こしやすく分枝結合(アミロペクチン)は老化の妨げになるとみられる。老化速度:穀類>馬鈴薯>甘藷>モチトウモロコシ
5.その他 : 十分に糊化されて、結晶種や凝集種となるような部分が少ないほど老化し難い場合が多い。100℃で5分間加熱した糊と、30分間加熱した糊では明らかに30分間加熱した場合の糊のほうが老化し難い。
老化防止技術
いかに老化抑制しても、少しずつ老化は進行する。実際には食品に含まれるすべてのデンプンをα態に維持していることはできない。
・炊飯後熱いうちに水分10%以下まで乾燥、あるいは油凋する。
例:α米、即席麺
・冷凍することで分子構造の変化を抑え、老化防止する。
例:冷凍食品、冷凍保存(和・洋菓子)等
・大量の糖(糖アルコール)を加えAwを低下させる。
例:すはま
・酵素でアミロースを切ることで、元のデンプンに戻らないようにする。
・その他
2.食品中の水分移動、香り成分の飛散
包装技術による保存性向上
冷凍技術による保存性向上
流通過程で本来食品中に含まれている水分が変化し、物性(レオロジー)が変わったり、香り成分が蒸発することを防止する。
例:せんべい等のナキ防止、香り成分の変化防止
煎餅をポリセロフィルム、KOPフィルム、アルミ蒸着フィルム、アルミ包装フィルムにいれ、更に脱酸素剤を入れて密封し、大きめのポリエチレン容器にいれ、容器の四隅に水を入れた容器を置き蓋をして、37℃で保存試験を行った。その結果、品質の劣化は
ポリセロ>KOP>アルミ蒸着>アルミ包装フィルム
の順であった。アルミ蒸着フィルムを用いたものは、物性的にはアルミ包装のものと遜色なかったが香りの劣化に差が見られた。