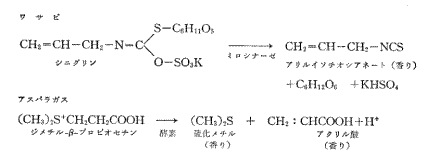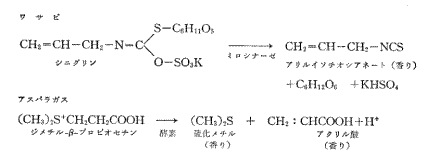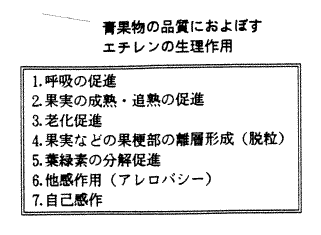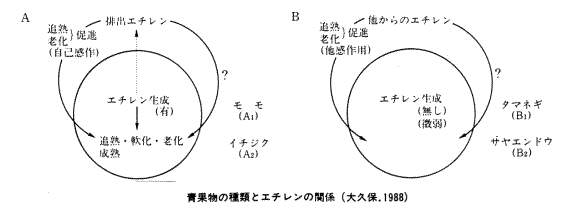Ⅰ.生物学的な要因
1.微生物的要因
人類は昔から色々と菌を利用してきた。お酒、味噌、醤油、ヨーグルト、納豆、くさや等がその代表である。一方食中毒に代表される人類にとって好ましくない菌類も存在する。ここに微生物管理技術の重要性がでてくる。
食品製造分野では従来、加熱などの処理による殺菌技術、あるいは低温保存技術、乾燥などによる水分活性低下技術、化学物質を添加して微生物を増殖させにくい環境にする技術等を駆使し、微生物制御が行われてきた。しかし、加工食品の低塩化、低糖化が進み、合成保存料が好まれない近年の消費者志向は、微生物制御の有効な手法と逆行した条件を作り出している。また、浅漬け漬け物に代表されるような加熱ができないもの、あるいは穏やかな加熱処理が要求される場合が多くなってきている。このように、現代の加工食品の微生物管理はより難しくなる一方、ますますその重要性を増してきており、新たな技術開発が望まれている。
食品は、蛋白質、炭水化物、脂質などの成分が色々な割合で混合されたものである。腐敗とは、微生物が増殖し、食品成分が分解作用により、変質を受け、食品として好ましくない状態に変化していく現象である。多くの場合腐敗すると食品の外観、物性、臭気、味などが変化し、官能的に判断できるが、食中毒菌によって汚染された場合、そのような変質が認められなくても、食中毒を起こす場合がある。腐敗における分解作用は微生物の種々の酵素によるものである。腐敗が進行してしまえば一見して腐敗していることが判る。
微生物による劣化を防ぐために一番大事なことは、有害微生物を①入れない、②汚さない、③増やさない事である。先ず菌数のできるだけ少ない原料を入手すること、次に加工工程中に外部からの菌の混入、加工機械等の汚れによる菌の混入を抑え、加工工程中における菌の増殖を抑制し、滅菌等の処理を行うことで、出荷時(保存開始時)の総菌数をできる限り少なくすることが重要である。
微生物の生育には、温度・水分活性・pHなどの至適条件があり、その条件を1つでもはずすことによって繁殖を防ぐことが可能となる。至適環境はほぼ以下の条件である。
一般的微生物生育条件
温度
|
一般細菌は0~30℃程度で繁殖する。胞子の場合でも、120℃10~120分で死滅。菌類の多くは60℃10分~30分程度で死滅する。カビや酵母は10~40℃程度で繁殖する。カビ胞子で60℃で5~10分程度で死滅、酵母は60℃10分程度で死滅する。 |
水分
水分活性(Aw) |
細菌では水分約15%以下で生育できないが、カビは乾燥に強く13%程度でも生育できる。
一般に細菌は1.00~0.95、カビは1.00~0.75程度で生育する |
pH
|
一般細菌はpH9~5程度、乳酸菌はpH8.5~3.5程度、カビはpH8~2程度で生育する。 |
酸素要求性
|
好気性菌、通性嫌気性菌、嫌気性菌など菌の種類により生育環境が異なる。 |
2.酵素的要因
酵素を利用した食品は身の回りに数多く存在する。
例えば、鰹の塩辛は鰹の内臓をきれいに洗い、塩と共に漬け込んだものである。時間の経過とともに内臓に含まれる酵素により自己消化を起こし、独特の風味を醸し出す。ワサビは摺り下ろすことで独特の辛みが発現する。椎茸も乾燥することで生の椎茸には無い、干し椎茸特有の香りが発現する。
わさびの辛み
アスパラの香り
椎茸の香り
レンチニン酸→(酵素:C-Sリアーゼ)→レンチオニン(乾燥椎茸の香り)
現在市販されている酵素類については、
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 食品総合研究所ホームページ(http://www.nfri.affrc.go.jp/)のお役立ちデーターベース(酵素一覧)が参考になります。
酵素による褐変
例:リンゴ、芋、レンコン等を放置したときに変色する現象(褐変)
一般的にはイモ、ゴボウなどに含まれるポリフェノール物質がポリフェノールオキシダーゼ(PPO)により酸化褐変する。また、紅茶のきれいな色は紅茶に含まれるカテキン類が萎凋処理されることで酸化重合しテアフラビンに変化したためである。
ポリフェノールの種類と主な食材
ポリフェノールとはフェノールがポリ(2個以上?がっている)構造をもっている物質で、一般にフラボノイド類と非フラボノイド類に分けられる。
フラボノイド類
・カテキン(テアフラビン、エピカテキンなど) : ワイン、茶、リンゴ、ブルーベリーに多く含まれる。
・アントシアン(アントシアン、シアニジンなど) : ブドウの実皮やムラサキイモ、ブルーベリー、黒豆、ナスなどの赤紫色をした植物体に多く含まれている色素成分。
・フラボノール(ルチン、ケルセチンなど):タマネギ、ソバなどに多く含まれる。
・イソフラボン(ダイジン、ゲニスチンなど):大豆や大豆加工商品(豆腐、納豆など)、クズ、くず粉などに含まれる。
・フラボン(アピゲニン、ルテオリンなど):パセリ、ピーマンなどに含まれる
・フラバノン(ナリンゲニン、ヘスペリジンなど):柑橘類に多く含まれる。
非フラボノイド類
・フェノール酸(カフェ酸、クロロゲン酸など) ;コーヒー、ジャガイモ、ゴボウなどに多く含まれる。
・リグナン(セサミン、セサミノールなど) : ゴマなどに多く含まれる。
・クルクミン(クルクミン、ショウガオールなど) : ウコン,ショウガなどに多く含まれる。
・エラグ酸 :イチゴ、ザクロ、ラズベリー、クルミなどに含まれる。
・クマリン : サクラの葉、パセリ、モモ、柑橘類に多く含まれる
・タンニン : 茶、赤ワイン、柿、バナナなどに含まれる渋味成分。
酵素的変色の防止
一般に、ポリフェノール、酸化酵素、酸素の存在下で発生
・pHと温度
pH4~7でよく作用する→クエン酸でpH4以下にしてマッシュルームの褐変防止
酵素失活→70~80℃に加熱
酵素活性抑制→5~10℃以下に保存
・酸素除去
PPOは酸化酵素 → 酸素を除去することで酸化抑制
・還元剤の利用(酵素活性抑制と酸化抑制)
VC+NaCl
失敗事例
・マイタケ入り茶碗蒸しが固まらない。
マイタケに含まれるタンパク分解酵素(アクチニジン)が卵のタンパク質を分解し凝固 を阻止した。
・パイナップルゼリーが溶解した。
ゼラチンを使用したためタンパク質が分解された。
・生のキウイをペースト状にし、カスタードクリームと混ぜ、菓子パンを試作したところ、 クリームが苦く食べられなかった。
キウイに含まれるタンパク分解酵素(エンドペクチナーゼ)がクリームを分解し苦味を 生じさせた。
生理学的要因
バナナ、キウイ等の追熟、
キウイを木の上で熟成させることができるだろうか?答えはNo である。キウイをリンゴなどと一緒にしておくと熟成する。これはリンゴなどの果物がエチレンガスを放出し、熟成するためである。
輸送中の熟成を押さえるためには、包装材料にエチレンガスを吸収するセラミックスを使用する等、CA制御が考えられる。