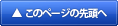誰も書かなかった簿記入門 第6版
試し読みページ(2/6)


簿記とは何か
簿記の歴史(1万円札と簿記の意外な関係)
「簿記」は、企業(会社や個人商店)が、日々の事業活動によって生じた収支等を帳簿に記録する
方法です。
なぜ簿記と言うようになったかについては諸説があり、実のところはっきりしないのですが、帳簿に記
録することから、帳簿の「簿」と記録の「記」の2文字から名付けられたと一般的には言われています。
簿記は、中世イタリアのベネチアにおいて、現在の簿記の仕組みが完成したと考えられています。
誰か一人が発明したとか、突然出来たというものではなく、それ以前からの人の知恵によって、その
仕組みが形作られました。
その当時の商人が行なっていた簿記を、1494年に出版された通称「スンマ」と呼ばれる数学書の中で
世界で最初に紹介したのが、その著者ルカ・パチョーリです。
このいわゆる西洋式簿記を日本で最初に紹介した本が、1873年(明治6年)に出版された「帳合之法」
(ちょうあいのほう)で、著者は1万円札の顔にもなっている福澤諭吉です。
日本でも江戸時代の商人は、「帳合」(ちょうあい)と呼んでいた独自の方法で帳簿に記録していました。
しかし、それは主に商品の売買代金やお金の貸し借りの記録であって、現在の簿記のように、事業活動
によって生じた収支等を一定のルールに従って記録するというようなものではありませんでした。
帳合之法は、西洋式簿記に関心を持った福澤が、アメリカの商業学校の簿記教科書を翻訳したもの
です。
帳合之法で福澤は、「bookkeeping」(ブックキーピング)を当時使われていた帳合と訳し、簿記の字を
使いませんでしたが、後に帳合に代わり簿記という言葉は急速に普及していきました。
方法です。
なぜ簿記と言うようになったかについては諸説があり、実のところはっきりしないのですが、帳簿に記
録することから、帳簿の「簿」と記録の「記」の2文字から名付けられたと一般的には言われています。
簿記は、中世イタリアのベネチアにおいて、現在の簿記の仕組みが完成したと考えられています。
誰か一人が発明したとか、突然出来たというものではなく、それ以前からの人の知恵によって、その
仕組みが形作られました。
その当時の商人が行なっていた簿記を、1494年に出版された通称「スンマ」と呼ばれる数学書の中で
世界で最初に紹介したのが、その著者ルカ・パチョーリです。
このいわゆる西洋式簿記を日本で最初に紹介した本が、1873年(明治6年)に出版された「帳合之法」
(ちょうあいのほう)で、著者は1万円札の顔にもなっている福澤諭吉です。
日本でも江戸時代の商人は、「帳合」(ちょうあい)と呼んでいた独自の方法で帳簿に記録していました。
しかし、それは主に商品の売買代金やお金の貸し借りの記録であって、現在の簿記のように、事業活動
によって生じた収支等を一定のルールに従って記録するというようなものではありませんでした。
帳合之法は、西洋式簿記に関心を持った福澤が、アメリカの商業学校の簿記教科書を翻訳したもの
です。
帳合之法で福澤は、「bookkeeping」(ブックキーピング)を当時使われていた帳合と訳し、簿記の字を
使いませんでしたが、後に帳合に代わり簿記という言葉は急速に普及していきました。