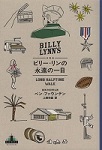
- 書 名 ビリー・リンの永遠の一日 (Billy Lynn's Long Halftime Walk)
- 作 者 ベン・ファウンテン (訳・上岡 伸雄)
- 出版社 新潮社
- 単行本 404ページ 2300円
[導入部]
ブラボー分隊の兵士たちはホテルからリムジンに乗ってテキサススタジアムに向かっていた。 その中に19才のビリーもいた。 イラクでの戦闘の様子がたまたまテレビの撮影クルーにより撮られアメリカで放映されたことにより、彼らは英雄視され、勝利の凱旋ツアーのためアメリカに戻された。 アメリカ中を二週間、8人の国民的ヒーローが回るのだ。 今日はダラス・カウボーイズの試合で行進することになっていた。
[採点] ☆☆☆☆
[寸評] 突然英雄に祭り上げられ国中を凱旋して回る若い兵士の目を通して、偉大なアメリカを希求し続ける国・国民の姿が描かれる。 戦地から戻った分隊の兵士たちと、彼らを称賛して止まないほら吹きとはったり屋の誇り高く臆病なタカ派の人々との対比が見事。 つかの間の帰郷の場面を除き全編スタジアムでの数時間だけの物語だが、冗長な感じは全くない。 また後半には熱狂の渦中でのビリーの一瞬の恋が熱い旋風のように描かれ青春小説としても良い。
[寸評]
宮部みゆきの江戸怪奇譚連作の第四編。
今回は100〜180ページほどの四話が収められている。
面白さでは定評のあるシリーズだが、今回も流石の上手さ。
特に二話と三話。
第二話は“ひだる神”という食いしん坊の神様が江戸の仕出し料理屋にとりつく話だが、ユーモラスで心温まる物語に仕立てられている。
一方、第三話“三鬼”は、語り手の武士の流転の境遇、赴任した村の謎めいた雰囲気と奇怪な出来事によりまさに一気読みの面白さだ。
[寸評]
元刑事が都内各地を循環バスで巡りながら、そこで出会う謎を解き明かすというトラベルミステリ連作八話。
バス巡りの行程、道路や街の風景が徹底取材で非常に詳しく描かれ、名所や旧跡にはそれぞれ蘊蓄が述べられる。
この辺りがかなりページ数を使っており、ちょっと冗長な感じで、東京在住でもない私には何かピンとこない。
“謎”は日常の小さなものだが、謎解きはよくそれだけの手がかりで解けるねという、名探偵ぶりが過ぎる感じでした。
[寸評]
40ページほどの連作短編8編。
今で言う“介護ヘルパー”さんのようなものが江戸時代にあったのか定かでないが、今も昔も人が長生きすれば老碌介抱も当然必要なわけで、家族だけでは背負いきれない分、本作の“介抱人”のような助けもあったのだろう。
お咲を取り巻く人々が素直で明確に描き込まれているし、どの話も介護にいろいろなケース、事情があって面白く読める。
後の方の話がお咲と母親との確執に比重が傾いてしまったのはちょっと不満。
[寸評]
地域の忌まわしい過去を掘り起こすサスペンスミステリでアメリカ探偵作家クラブ賞受賞作。
物語は1952年のアニーが主体のパート、36年のアニーの母サラとその妹ジュナが主体のパートの2つに分かれ、交互に語られる。
終盤の、過去が一挙に呼び覚まされるあたりは、怒濤の展開で息をつがせない。
しかし序盤からあえて説明が少ない書き方で、登場人物の関係性もごちゃごちゃしていて、なかなか物語世界に入り込むことができなかった。
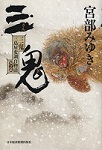
[導入部]
三島屋は江戸は神田の袋物屋。
主人の伊兵衛とおかみのお民が興した店で、江戸の洒落者達の人気を集めている。
二年前の秋口から伊兵衛の姪のおちかという娘が一緒に住んでいる。
おちかは店で働くと共に、伊兵衛の命を受けて、三島屋の客間に一人の語り手を招き入れては、不思議な話や恐ろしい話を聞き出す役目をこなしている。
今回やって来た話し手は、まだ十二、三歳の女の子だった。
[採点] ☆☆☆☆★
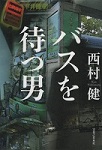
[導入部]
警視庁を定年退職して10年。
その後交通安全協会にも籍を置いたが、数年前に辞めた。
仕事人間だった私が勤務を辞めてしまうと途端にやることがなくなった。
特に困るのが、妻の料理教室が我が家で開催される毎週水曜日。
公園で一日ぼんやり過ごすことが多かった。
そんなとき妻から、都内のバスや地下鉄に乗り放題のシルバーパスを使って、あちこち足を伸ばしてみるのはどうかと提案された。
[採点] ☆☆★
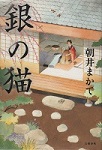
[導入部]
天保年間、江戸の町でお咲は、身内に代わって年寄りの介抱を助ける奉公人の「介抱人」をしている。
三日の間、泊まり込みで世話をする仕事で、口入屋の鳩屋からもらう給金は並の女中奉公よりはるかにいいが重労働だ。
加賀屋の八十五歳の隠居の世話を終え、鳩屋で世話の様子を奉公帳に記したお咲は、疲れた体で長屋の自宅に向かう。
お咲は介抱人をして母親の佐和が作った借金を返している。
[採点] ☆☆☆☆

[導入部]
1952年、ホールラン家の長女アニーは十五歳と十六歳の中間の日を迎えていた。
ヘイデン郡の娘たちは、その日の真夜中に井戸を覗き込むと将来の伴侶が見えるという言い伝えがあるのだ。
この10年ほとんどの娘がファルカーソン家の井戸に向かっていた。
しかしアニーはベイン家の井戸に向かうことにした。
ホールランの人間はベイン家には近づかなかった。
ジュナ叔母さんが両家の憎しみの始まりだった。
[採点] ☆☆☆
 ホームページへ
ホームページへ  私の本棚(書名索引)へ
私の本棚(書名索引)へ  私の本棚(作者名索引)へ
私の本棚(作者名索引)へ