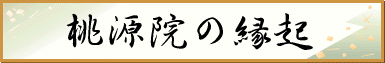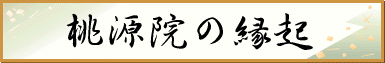|
『開基さま』とは、桃源院を始めて建立された方である。
隠居して、静岡の北川辺りに住まいされていたので、通称『北川殿』と呼ばれている。北川殿は今川吉忠の側室で、今川義元の祖母にあたる。北川殿の兄は伊勢新九郎と称し、後に北条早雲となった方である。
義忠公は、「応仁の乱」に出陣して大功があった。義忠公は当時、二十九歳であり、乱が終わると部下より先に故郷静岡に向かった。数名の従者と、塩見坂〔今の小笠郡小笠町南山〕を通る時、百姓一揆に逢い、攻撃を受けて戦死してしまった。
今川家を継ぐべき長男『龍王丸』(後、北条氏親)は、当時四歳であったので、相続問題で、今川家中が二つに分かれ争いが起きた。
北川殿は龍王丸の実母なので、幼い龍王丸を連れて、駿河国志多郡小川郷〔今の焼津市〕に住む小河法永長者の館に身を寄せた。
この頃、狐ヶ崎に住む上杉政憲あと、関東の太田道灌の軍六百余騎が、龍王丸を護持しようと、駿府(静岡市)に待機していた。しかし、北川殿の兄伊勢新九郎(後の北条早雲)が、妹の北川殿と共に、龍王丸をしっかり護っているのをみて、この両名に、任せて、軍を引き上げていった。
龍王丸は、十一年間この館に住み、十五歳になった時、駿府に帰り今川家を相続した。
この功労により、根方の興国寺城の城主となり、やがて伊豆韮山に入り、北条氏の基礎を固めたのである。
『北川殿』は、この間に今川家の菩提を葬ると共に兄北条家の武運を祈願して、駿河の国と伊豆の境に当たる大平の地に桃源院開山興国玄晨大和尚さまを請して、寺院の建立を依願した。早速、奉行所を通じて、大平の庄屋、権之輔修理之亮左門の三名に建立するように命があり、一寺を建立した。
大平に山を開いたということで、山号を大平山、寺名を桃源院と称した。
開山興国玄晨大和尚は、琵琶湖畔新豊院にて仏門に入り、この寺にて修行中、北川殿の請により、桃源院を建立し開山となる。建立した翌年、入仏式を行った。
|