■遺留分(いりゅうぶん)
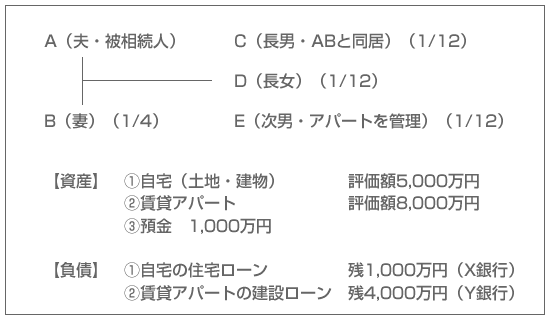 《遺産分割の方法》のページで扱った上記のケースで、Aが次のような遺言を残していたらどうなるでしょうか。 《遺産分割の方法》のページで扱った上記のケースで、Aが次のような遺言を残していたらどうなるでしょうか。
私の財産を、全て、Cに相続させる。
自分の財産を、自分の死後にどのように分け与えるかは、遺言によって自由に決められますから、このような遺言も有効です。したがって、Cは、自宅も、アパートも、預金も、全て1人で相続できることになります(他方、借金は、銀行の同意がない限り、相続人がそれぞれの法定相続分に従って、分割して引き継ぐことになります。)。
しかし、親からある程度の財産を受け継ぐことが、子供達の生活の安定のためには必要な場合が多いですし、同じ立場にある相続人間であまりに不公平な結果になるのも望ましいとは言えません。
そこで、民法は、一定範囲の相続人に、最低限の相続財産の承継を保障する制度をもうけています。この権利のことを、遺留分(権)といいます。
■遺留分
▽ 遺留分は、兄弟姉妹にはありません。
▽ 遺留分を主張するかどうかは、各相続人の自由です。
▽ 遺留分を主張する場合には、例えば上記のような遺書の存在を知ったときから1年以内に、Cに対して意思表示をする必要があります(これを、遺留分減殺(げんさい)請求権の行使といい、配達証明付内容証明郵便で行うのが一般です。)。
▽ 遺留分の割合は、法定相続分の半分とお考え下さい(直系尊属のみが相続人の場合には、法定相続分の3分の1です。)。
では、上記のケースで、B・D・Eの遺留分割合を計算してみましょう。
法定相続分は、妻Bが2分の1、子供D・Eが6分の1ですから、それぞれの遺留分は、Bが4分の1、D・Eが12分の1となります。
遺産全体の評価額(資産−負債)は、9,000万円ですから、各人の具体的な遺留分は、
B =9,000万円×1/4=2,250万円
D・E =9,000万円×1/12=750万円
となります。
そこで、BやD・Eは、この遺留分に見合うだけの財産を引き渡すように、Cに対して請求できることになります。
■生前贈与と持ち戻し
上記のケースで、例えばEが、Aの生前に、住宅建築資金の一部として1,000万円の贈与を受けていたような場合、この生前贈与分は、遺留分計算のために持ち戻します。生前贈与は、相続の前倒しと考えられるからです。
仮に、生前贈与の時と、A死亡の時で、貨幣価値が変わらないとした場合、遺留分計算のための基礎となる財産は、
A死亡時の資産 合計1億4,000万円
+ Eの生前贈与分 1,000万円(持ち戻し)
− A死亡時の負債 合計5,000万円
───────────────────
基礎となる財産 1億円
となり、それぞれの具体的な遺留分は、
B=1億円×1/4=2,500万円
D・E=1億円×1/12=833万3333円
となります。
したがって、Eは既に遺留分金額を超える生前贈与を受けていますから、Cに対してこれ以上の遺留分の請求をすることができないことになります(なお、このケースでは、Eは遺留分を超える約167万円を返す必要はありません。)。
どうでしょう。お分かり頂けましたか?
遺留分に関する争いは、時として複雑な計算や立証が必要になりますし、上記のような遺言書に不満や疑問を抱いたDやEが、遺言無効確認訴訟を提起することもよくあります。遺留分減殺請求権の行使期間が1年と短いこともありますので、お早めにご相談頂ければと思います。
|

