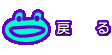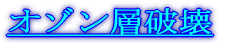
2004-6-07
仛仛丂僆僝儞憌偺攋夡偼恑傫偱偄傞丂仛仛
僆僝儞憌偲偼丄崅搙侾侽乣俆侽俲倣偺斖埻(惉憌寳)偵偁傝丄懳棳寳偺奜懁傪庢傝姫偔傛偆偵懚嵼偟偰偄傞丅
崅搙俀俆俲倣晅嬤偺擹搙偑嵟戝偲側傞丅
偲偼偄偊丄偦偺検偼侽亷丒侾婥埑偵埑弅偟偰壖偵丄抧忋晅嬤偵帩偭偰偒偨偲偟偰傕丄岤偝偼嬐偐俁倣倣掱搙
偺敄偄憌偵側偭偰偟傑偄傑偡丅
偩偐傜丄旕忢偵婓敄側憌偲偟偰懚嵼偟偰偄傞傢偗偱偡偹丅
僆僝儞偼丄巁慺尨巕偑3偮偑寢崌偟偨傕偺偱偡偑丄惉憌寳偵偁傞巁慺暘巕偑嫮椡側巼奜慄傪庴偗偰暘夝偟丄
偦傟偑嵞傃巁慺暘巕偲寢崌偡傞偙偲偱嶌傜傟傞偑丄抧忋晅嬤偵偁傞偲岝壔妛僗儌僢僌偺尨場暔幙偵側傝丄
惗暔偵偲偭偰偼栵夘幰偱偡偑丄惉憌寳偵偁傞僆僝儞偼柍偔偰偼側傜側偄懚嵼偩丅
偙偺僆僝儞憌偺栶妱偼丄旕忢偵廳戝偱抧媴忋偺惗暔偵偲偭偰桳奞側巼奜慄傪媧廂偟偰偔傟傑偡丅
偟偐偟丄偙偺僆僝儞憌偑丄崱丄恖岺揑偵嶌傜傟偨僼儘儞摍偺壔妛暔幙偱攋夡偝傟傛偆偲偟偰偄傞偺偱偡丅
僆僝儞憌偑攋夡偝傟傞偲丄僸僩偱偼旂晢偑傫傗敀撪忈偑憹壛偟丄懠偺摦怉暔偵傕庬偺懚朣偵娭傢傞廳戝側
埆塭嬁傪媦傏偟傑偡丅
偐偮偰丄尨巒抧媴偵偼巁慺傕僆僝儞憌傕懚嵼偟傑偣傫偱偟偨丅
偦偺偨傔丄桳奞巼奜慄偑抧忋偵崀傝拲偓丄惗暔偑棨忋偱惗懚偡傞偙偲偼偱偒傑偣傫偱偟偨丅
偲偙傠偑丄奀偱岝崌惉傪偡傞僶僋僥儕傾偑抋惗偟偨偙偲偱丄巁慺偑惗嶻偝傟師戞偵擹搙傪崅傔傞偲偲傕偵
忋嬻偱偼僆僝儞憌偑宍惉偝傟傞偵帄傝傑偟偨丅
偦偺寢壥丄桳奞巼奜慄偑尭彮偟棨忋偱傕惗暔偑惗懚偱偒傞傛偆偵側傝傑偟偨丅
偦傟偑丄宍惉偝傟傞偵帄傞傑偱偺摴偺傝偼壗壄擭偲偄偆丄婥偺墦偔側傞傛偆側帪娫偑旓傗偝傟傑偟偨丅
偟偐偟丄偦偺婱廳側僆僝儞憌傪恖椶偼嬐偐昐擭偵傕枮偨側偄抁帪娫偺偆偪偵攋夡偟傛偆偲偟偰偄傞偺偱偡丅
恖椶偺丄偙傫側恎彑庤側墶朶偼嫋偝傟偰偄偄偺偱偟傚偆偐丠
杊屼偺庤抜傪帩偨側偄懠偺惗暔偨偪偼丄懚朣偺婋婡偵偝傜偝傟偰偄傑偡丅
愱栧壔偵傛傟偽丄僆僝儞憌攋夡偺塭嬁偼丄傑偩巒傑偭偨偽偐傝偱丄崱屻偳偙傑偱怺崗側旐奞偵尒晳傢傟傞偐丄
傑偨丄偄偮廔懅偡傞偺偐傕掕偐偱偼偁傝傑偣傫丅
2004-6-08
仛仛丂僆僝儞憌偺攋夡暔幙僼儘儞丂仛仛
丂僼儘儞偼丄侾俋俀俉擭偵丄暷俧俤幮偵傛傝奐敪偝傟丄偦偺屻丄僨儏億儞幮偵傛傝戝検偵惗嶻偝傟傞傛偆
偵側傝尰嵼偵帄偭偰偄傞丅
丂柍撆丒柍怓丒柍廘丒晄擱惈丒壢妛揑偵埨掕偟偰偄傞側偳丄帄傟傝恠偔偣傝偺乽柌偺暔幙乿偲偟偰丄
偁傜備傞暘栰偱棙梡偝傟丄変乆偺惗妶偵怺偔怹摟偟偰偒傑偟偨丅
丂庡側棙梡愭偼丄椻憼屔傗僋乕儔乕偺椻攠丒僗僾儗僀偺暚幩嵻丒敿摫懱偺愻忩嵻丒儅僢僩儗僗傗抐擬嵽側偳偺
尨椏偲側傞敪朇僂儗僞儞傪嶌傞夁掱偱戝検偵巊梡偝傟偨丅
丂偟偐偟丄侾俋俈係擭丄暷僇儕僼僅儖僯傾戝妛偺儘乕儔儞僪偲儌儕僫乕嫵庼傜偵傛傝丄僼儘儞偑惉憌寳偵傑偱
払偟偰僆僝儞憌傪攋夡偟偰偄傞壜擻惈偑偁傞偲丄敪昞偝傟偨偺傪敪抂偵丄尋媶傗娤應偑懕偗傜傟帠幚偱偁傞偙偲
偑幚徹偝傟偨丅
丂偦偺寢壥丄尰嵼丄抧媴揑婯柾偱僼儘儞偺婯惂偑恑傫偱偄傞丅
丂偟偐偟丄傂偲岥偵乽僼儘儞乿偲偄偭偰傕條乆側庬椶偑偁傞丅
嘆僋儘儘僼儖僆儘僇乕儃儞椶乮俠俥俠乯
扽慺丒僼僢慺丒墫慺偐傜側傝丄捠徧乽摿掕僼儘儞乿偲屇偽傟偰偄傞丅
丂僆僝儞憌傪攋夡偡傞嶌梡偑傕偭偲傕嫮偔丄侾俋俉俈擭乽儌儞僩儕僆乕儖媍掕彂乿偵傛傝丄偙偺婯惂偑奐巒偝傟丄
侾俋俋俀擭乽戞係夞掲栺崙夛媍乿偱侾俋俋俆擭侾俀寧俁侾擔傪傕偭偰愭恑崙偱偺惗嶻偼慡攑偝傟偨丅
丂(搑忋崙偼俀侽侾侽擭傑偱偵慡攑)
丂尰嵼偼丄俠俥俠偺戙傢傝偵乽戙懼僼儘儞乿偵堏峴偑恑傫偱偄傞丅
丂俠俥俠亅侾侾(嬈柋梡戝宆椻搥嬻挷婡婍丒敪朅嵻)
丂俠俥俠亅侾俀(椻憼屔丒僇乕僄傾僐儞丒敪朅嵻)
丂俠俥俠亅侾侾俁(愻忩嵻)
丂偙傟傑偱偵丄惗嶻偝傟偨乽摿掕僼儘儞乿偺憤検偼俀侾侽侽枩倲埲忋偁傞偲塢傢傟偰偄傞丅
丂偦偺栺俋侽亾偼偡偱偵戝婥偵曻弌偝傟偰偍傝丄巆傝侾侽亾偼婡婍偺拞偵巆懚偟偰偄傞丅
丂戝婥偵曻弌偟偨撪偺侾侽亾偑丄偡偱偵惉憌寳(僆僝儞憌)偵摓払偟埆偝傪偟偰偄傞傢偗偱偡丅
丂偨偭偨侾侽亾偱偡傛丅
丂傑偩俋侽亾偼偙傟偐傜丄惉憌寳偵摓払偡傞傫偱偡傛丅
丂戙懼僼儘儞偵偼丄
嘇僴僀僪儘僋儘儘僼儖僆儘僇乕儃儞(俫俠俥俠)
丂扽慺丒僼僢慺丒墫慺偵悈慺傪壛偊偨傕偺偱丄僆僝儞憌偵摓払偡傞慜偵暘夝偟丄僆僝儞憌攋夡偵偼帄傜側偄偲
塢傢傟偰偄傑偡偑丄慡偰偑暘夝偡傞偲塢偆傢偗偱偼側偄偺偱丄俀侽俀侽擭傑偱偟偐惗嶻偑擣傔傜傟偰偄側偄丅
丂擔杮崙撪偺庡梫僄傾僐儞儊乕僇乕偱偼丄婇嬈偺帺庡揑側搘椡偵傛傝丄偦偺巊梡傪慜搢偟偟偰拞巭偟偰偄傞婌偽偟偄
曬崘傕偁傝傑偡丅
丂俫俠俥俠亅俀俀(僄傾僐儞丒椻搥嬻挷婡婍)
丂俫俠俥俠亅侾係侾a丒侾係侾b(敪朅嵻)
丂俫俠俥俠亅俀俀俆(愻忩嵻)
嘊僴僀僪儘僼儖僆儘僇乕儃儞(俫俥俠)
丂扽慺丒僼僢慺丒悈慺偐傜側傝墫慺傪娷傫偱偄側偄偺偱僆僝儞憌攋夡嶌梡偼柍偄丄偟偐偟丄擇巁壔扽慺偺悢愮攞丒悢枩攞
偺壏幒岠壥偑偁傞偙偲偑巜揈偝傟偰偍傝丄乽戙懼僼儘儞乿偩偐傜埨慡偩偲塢偆傕偺偱偼側偄丅
丂備偊偵丄柍惂尷偵巊梡傪懕偗傞偙偲偼丄偄偨偢傜偵娐嫬栤戣傪挿堷偐偣傞偩偗偱偡丅
丂乽僲儞僼儘儞乿壔偵岦偗偰偺婇嬈搘椡傪婜懸偡傞偙偲偼栜榑偱偡偑丄堦斒巗柉偺僼儘儞娭楢彜昳偵懳偡傞擣幆傪崅傔丄
偦偺庢埖傗攑婞偵娭偟偰丄乽椙偒抧媴巗柉乿偲偟偰偺棫応偵棫偭偰丄儖乕儖傪姰慡偵弲庣丒棜峴偡傞偙偲傪丄偍婅偄偟偨偄丅
2004-6-09
仛仛丂僆僝儞憌偺攋夡偺儊僇僯僘儉丂仛仛
丂僆僝儞憌傪攋夡偡傞壔妛暔幙偵偼僼儘儞丒僴儘儞丒巐墫壔扽慺丒僩儕僋儘儘僄僞儞丒廘壔儊僠儖側偳偑偁傞丅
丂偙傟傜偼丄戝婥拞偵曻弌偝傟偰傕暘夝偝傟偢丄偦偺傑傑丄挿偄帪娫乮俆乣侾侽擭掱搙乯偐偗偰惉憌寳偵摓払偡傞丅
丂偦偙偱嫮偄巼奜慄偵偁偨傞偲丄弶傔偰暘夝偟偰墫慺尨巕傗廘慺尨巕傪曻弌偟傑偡丅
丂偙偺墫慺尨巕傗廘慺尨巕偑僆僝儞憌傪攋夡偡傞偺偱偡偑丄偦偺巇慻傒傪丄僼儘儞傪椺偵愢柧偡傞偲丄
侾丏惉憌寳偵徃傝偮傔偨僼儘儞偼嫮偄巼奜慄傪庴偗傞偲丄暘夝偟偰墫慺尨巕傪曻弌偟傑偡丅
俀丏墫慺尨巕偼丄僆僝儞拞偺巁慺尨巕偲寢傃偮偔偙偲偵傛傝丄僆僝儞傪攋夡偟傑偡丅
丂乮僆僝儞偲墫慺尨巕偑斀墳偟偰堦巁壔墫慺偲巁慺偵側傞丅丂俷?亄俠倢仺俠倢俷亄俷?乯
俁丏巁慺尨巕偲寢傃偮偄偨墫慺尨巕偼廃曈偵嶶嵼偡傞巁慺尨巕偲寢傃偮偒丄嵞傃墫慺尨巕偑棧傟丄暿偺僆僝儞傪攋夡偡傞丅
乮俫俠俴丂仺丂俫亄俠倢丒俠倢亄俷?丂仺丂俠倢俷亄俷?丒俷?亄俠倢亖俠倢亄俷?乯
丂偙傟傪嵺尷側偔孞傝曉偡偙偲偵側傝傑偡丅
丂栵夘側丄偼側偟偱偡偹丅(~_~;)
丂愱栧壠偵傛傟偽丄
丂惉憌寳偺丄僆僝儞偺憤検偼俁俁壄僩儞丅
丂擭娫攋夡憤検偼俉,侽侽侽枩僩儞乮悇掕乯
丂偙傟傑偱偵丄惗嶻偝傟偨乽摿掕僼儘儞乿偺憤検偼俀侾侽侽枩僩儞埲忋丅
丂偦偺栺俋侽亾偼偡偱偵戝婥偵曻弌偝傟偰偄傞丅乮侾丆俉侽侽枩僩儞乯
丂巆傝侾侽亾偼婡婍偺拞偵巆懚偟偰偄傞丅
丂戝婥偵曻弌偟偨撪偺侾侽亾乮俀侽侽枩倲埲忋乯偑丄惉憌寳偵摓払偟偰偄傞丅
丂偙傟偐傜丄摓払偡傞偱偁傠偆検偼丄彮側偔尒愊傕偭偰傕侾丆俆侽侽枩僩儞丅
丂偙偺悢抣傪尒偰丄婥偯偐傟傞偲巚偄傑偡偑丄
丂偙偺栤戣偑丄偄偐偵戝偒偄偐偑巉偊傞偲巚偄傑偡丅
2004-6-14
仛仛丂僆僝儞儂乕儖丂仛仛
丂撿嬌偺弔乮俋寧崰乯偵偼忋嬻偺惉憌寳偺僆僝儞偑杦傫偳側偔側偭偰寠偑奐偄偨忬懺偲側傞晹暘偑惗偠傑偡丅
丂偙傟傪乽僆僝儞偺寠乿僆僝儞儂乕儖偲偄偄傑偡丅
丂撿嬌偼俈寧乣俉寧偵搤傪寎偊丄懢梲偑慡偔婄傪尒偣側偄栭偺悽奅偵側傝傑偡丅
丂傑偨丄偙偺帪婜乽嬌塓乿偲屇偽傟傞撿嬌摿桳偺嫮偄晽偑悂偒峳傟丄偦偺椞堟偼丄廃埻偲偼妘棧偝傟偨忬懺偵側傝丄
亅俋侽亷埲壓偵傕側傞偦偆偱偡丅
丂偙偺帪丄戝婥拞偺嬐偐側悈暘傕昘偺棻偵側偭偰嬌惉憌寳塤傪宍惉偟傑偡丅
丂偙偺昘偺棻偼丄墫慺娷桳暔幙偲悈偺崿崌暔偱弌棃偰偄傞偲峫偊傜傟偰偄傑偡丅
丂偙偺昘棻偑挿偄嬌抧偺搤偺娫偵丄壔妛斀墳偑婲偒墫慺尨巕偑暘棧偝傟傞丅
丂弔偑棃傞傑偱偼僆僝儞傪攋夡偡傞偙偲偼側偄偑丄弔偺朘傟偲偲傕偵嫮椡側巼奜慄傪梺傃傞偙偲偱丄岝壔妛斀墳偑
婲偙傞傛偆偵側傝丄攋夡嶌梡傪偡傞傛偆偵側傞丅
丂傑偨丄嬌塓撪晹偺僼儘儞偑暘夝偟偰墫慺尨巕偑旘傃弌偡偙偲偱丄偙偺椉幰偺憡忔嶌梡偱嬌惉憌寳塤偺拞偼楢嵔揑偵丄
挿帪娫僆僝儞偑攋夡偝傟傞偲偺偙偲偱偡丅
偙偺尰徾偱丄嬌塓撪偺僆僝儞偼偙偲偛偲偔攋夡偟恠偝傟偰偟傑偄乽僆僝儞儂乕儖乿偲偄偆嫲傞傋偒忬懺偵側傝傑偡丅
丂堦曽丄杒嬌抧曽偱偼撿嬌傎偳掅壏偵偼側傜偢丄昘寢偲壔妛揑夁掱偑恑峴偡傞偨傔偺忦審偑挿婜娫丄埨掕揑偵懕偔
椞堟偑懚嵼偟側偄偨傔丄偦傟掱偱偼側偄偑丄僆僝儞憌偺攋夡偼拝幚偵恑峴偟偰偍傝丄擔杮偱傕丄杒奀摴忋嬻偼尭彮
孹岦偵偁傝塭嬁偑怱攝偝傟偰偄傞丅
丂娐嫬徣儂乕儉儁乕僕丂http://www.env.go.jp/index.html
丂乽僆僝儞憌摍偺娔帇寢壥偵娭偡傞擭師曬崘乿偱徻偟偔妋擣偱偒傑偡丅
丂嫽枴偺偁傞曽偼俴倝値倠偟偰丄尒偰偔偩偝偄丅
2004-6-10
仛仛丂巼奜慄偺嫼埿丂仛仛
丂懢梲岝慄偼丄旕忢偵峀偄斖埻偺攇挿偺岝傪娷傫偱偄傑偡丅
丂偦偺拞偱巹偨偪偺栚偵懆偊傜傟傞偺偼丄攇挿400(巼)乣700(愒)僫僲丒儊乕僩儖偺壜帇岝慄偲偄偆椞堟偩偗偱偡偑丄
丂偦偺奜懁偵傕尒偊側偄岝偺悽奅偑峀偑偭偰偄傑偡丅
丂400僫僲丒儊乕僩儖傛傝抁攇挿偺巼奜慄椞堟(UV)偲700僫僲丒儊乕僩儖傛傝挿攇挿偺愒奜慄椞堟(IR)偑偁傝傑偡丅
丂巼奜慄偼丄偝傜偵攇挿偵傛傝UV-A丒UV-B丒UV-C偺俁庬椶偵暘椶偝傟傑偡丅
丂(1僫僲丒儊乕僩儖=10壄暘偺1儊乕僩儖)
丂(UV=僂儖僩儔丒僶僀僆儗僢僩)
丂(IR=僀儞僼儔丒儗僢僩)
丂侾丏倀倁亅俙(攇挿315僫僲丒儊乕僩儖)埲忋
丂丂攇挿偺傕偭偲傕抁偄巼奜慄偱惉憌寳傪慺捠傝偟偰抧忋偵摓払偟傑偡丅
丂丂旂晢傪崟偔偟偨傝僔儈傪嶌傞偙偲傕偁傞偑丄價僞儈儞俢偺惗惉傪彆偗傞側偳偺嶌梡傕偁傝丄
丂丂偳偪傜偐偲尵偊偽婋尟惈偼彮側偄巼奜慄偲偄偊傞丅
丂俀丏倀倁亅俛(315乣280僫僲丒儊乕僩儖)
丂丂巼奜慄偺拞偱偼拞娫攇挿偱丄偦偺戝晹暘偑僆僝儞憌乮俁侽乣俀侽俲倣晅嬤乯
丂丂偵傛偭偰媧廂偝傟偰偄傞偨傔丄僆僝儞憌偑攋夡偝傟傞偲抧忋偵崀傝拲偖傛偆偵側傝傑偡丅
丂俁丏倀倁亅俠(攇挿280僫僲丒儊乕僩儖)
丂丂攇挿偑抁偔丄杮棃側傜偽嵟傕婋尟側巼奜慄偱偡偑丄傎偲傫偳偑忋嬻丄悢昐俲倣乣俁俆俲倣偵斾妑揑懡偔
丂丂懚嵼偡傞巁慺暘巕傗婓敄側僆僝儞偵媧廂偝傟抧忋偵偼摓払偟偰偄側偄偲偄傢傟偰偄傑偡丅
丂丂僆僝儞憌偑攋夡偝傟偨偲偟偰傕巁慺偑媧廂偡傞偺偱怱攝偼側偄丅
丂偙偺傛偆偵丄桳奞晹暘偑搒崌傛偔僇僢僩偝傟傞巇妡偗偲側偭偰偄偨偺偱丄惗暔偑抧忋偱惗懚偱偒傞娐嫬偑挿偄偙偲
曐偨傟偰偒偨丅
丂偟偐偟丄偙偙偵偒偰丄僆僝儞憌攋夡偺壛懍偱嫸偄偑惗偠偰偒偰偄傞偺偱偡丅
丂摿偵丄怱攝偝傟偰偄傞倀倁亅俛偼抧忋偵崀傝拲偖偲丄師偺傛偆側塭嬁傗栤戣偑惗偯傞丅
丂仛恖傊偺塭嬁
丂丂僆僝儞憌攋夡偵傛傞桳奞巼奜慄偺憹壛偼丄僸僩偺偐傜偩偺嵶朎偵彎傪偮偗娽偺昦婥傗旂晢僈儞傪堷偒婲偙偡傎偐丄
丂丂柶塽椡傪掅壓偝偣傑偡丅
丂仛摦怉暔傊偺塭嬁
丂丂旝惗暔偼桳奞巼奜慄偺塭嬁傪庴偗傗偡偔丄僾儔儞僋僩儞傗偝傑偞傑側摦怉暔偺惉挿偑偝傑偨偘傜傟丄嫏妉崅偺尭彮
丂丂傗擾嶌暔偺尭廂側偳丄怘椘惗嶻偵戝偒側塭嬁偑弌傑偡丅
丂仛婥岓傊偺塭嬁
丂丂惉憌寳偺戝婥偺娐嫬偑曄壔偟丄嬊抧揑偵戝塉偵側偭偨傝丄戜晽偑戝宆壔偟偨傝偲偄偭偨塭嬁偑偁傜傢傟傑偡丅
丂丂媡偵姳偽偮偵側傞抧堟傕弌偰偔傞偙偲偑偁傝傑偡丅
丂丂傑偨丄巼奜慄偑抧忋偵崀傝拲偓丄抧忋晅嬤偺巁慺偑斀墳偟丄懳棳寳僆僝儞偑憹偊偰岝壔妛僗儌僢僌偺尨場偵傕側傝傑偡丅
丂仛暔幙傊偺塭嬁
丂丂寶暔偺壆崻嵽丒暻嵽側偳丄捈幩擔岝傪庴偗傞晹嵽偼塭嬁傪庴偗傞嫲傟偑偁傞丅
丂丂偙傟傑偱丄堦斒揑偵巊梡偝傟偰偒偨嵽椏偼丄偦偺傑傑偱偼丄曄怓丒懴媣惈偑掅壓偡傞偺偱丄巊梡偱偒側偔側傞壜擻惈偑偁傝傑偡丅
丂丂摿偵丄僾儔僗僠僢僋丒揾椏丒慇堐丒僑儉側偳偺慺嵽偑塭嬁傪庴偗傑偡丅
丂丂偙傟偐傜丄壞杮斣傪寎偊傑偡丅
丂丂巼奜慄検傕憹壛偟傑偡丅
丂丂彈惈彅孨丄婥徾挕偺揤婥梊曬偩偗偱側偔巼奜慄梊曬偵傕拲栚偟傛偆両両
丂
2004-6-21
仛仛丂乽戝婥偺憢乿傪傆偝偖婋尟側僼儘儞丂仛仛
丂寶暔偵偼憢偑偁偭偰丄嵦岝傗嬻婥偺弌偟擖傟偵栶棫偭偰偄傑偡丅
丂抧媴偵傕乽戝婥偺憢乿偲屇偽傟傞憢偑偁偭偰丄抧媴偺擬傪塅拡嬻娫傊摝偑偡廳梫側栶栚傪壥偨偟偰偄傑偡丅
丂愱栧壠偵傛傟偽丄懢梲岝慄偼戝婥傪慺捠傝偟偰抧昞偵摓払偟丄傑偢抧昞傪壏傔傑偡丅
丂壏傔傜傟偨抧昞偼丄戝婥偺曽岦偵愒奜慄偲偄偆偐偨偪偱擬傪曻弌偟傑偡丅
丂偙偺帪偺丄曻幩僄僱儖僊乕偼係乣俁侽儅僀僋儘儊乕僩儖偺愒奜慄偱偡丅
丂偙傟傪丄僉儍僢僠偡傞偺偑壏幒岠壥僈僗偱偡偑丄係乣俁侽儅僀僋儘儊乕僩儖偺偆偪帺慠奅偵尦乆偁傞壏幒岠壥僈僗
乮擇巁壔扽慺丒儊僞儞丒悈忲婥側偳乯偼侾俀儅僀僋儘儊乕僩儖埲壓偺愒奜慄偺杦偳傪媧廂偟傑偣傫丅
丂廬偭偰丄抧媴偺懡偔偺擬偼塅拡嬻娫傊曻幩偝傟傑偡丅
丂乽夁嫀壗壄擭偼丄偢乣偭偲曻幩偝傟偰偄傑偟偨丅乿偲偄偆昞尰偺曽偑丄偄偄偺偐傕偟傟傑偣傫丅
丂偮傑傝丄奐偐傟偨乽戝婥偺憢乿偑丄婡擻偟偰偄偨偺偱偡丅
丂偙偺奐偐傟偨乽戝婥偺憢乿偑丄抧媴偺岻柇側壏搙挷愡僔僗僥儉偺廳梫側栶妱傪壥偨偟偰偄傑偟偨丅
丂偟偐偟丄僼儘儞丒僴儘儞椶偼丄偙偺椞堟偺愒奜慄傪嫮偔媧廂偡傞摿惈傪帩偭偰偄傑偡偐傜丄帺慠偑壏搙挷愡偺偨傔偵
巆偟偰偄偨乽戝婥偺憢乿傪嵡偄偱偟傑偆宍偲側傝丄嬌傔偰婋尟側暔幙偲偄偊傞偺偱偡丅
丂偙傟偑丄尰嵼栤戣偵側偭偰偄傞乽抧媴壏抔壔乿傪壛懍偝偣傞丄廳戝側尨場偵側偭偰偄傞偺偱偡丅
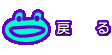
![]()