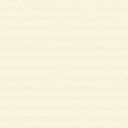
なぜ白髪に!?
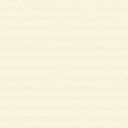
白髪の「今」
白髪は、薄毛、男性型脱毛症とともに、遺伝的な要素が強いとされるものの
、その原因は、いまだ藪の中。
医学的な研究がなかなか進まず、解明されていなかった。
ところがここへきて、さまざまな角度からの研究が効果をあげてきている。
その成果のひとつに、京大グループが発見した色素幹細胞毛がある。
色素幹細胞とは、毛髪に色をつける色素細胞(メラノサイト)のモトとなるもので、
これまでは理論的には存在するといわれてきたものの、
実際は存在や場所の確認ができていなかった。
今回の発見によって、白髪のできる仕組みの解明がさらに一歩進むものと期待されている。
もうひとつは、花王の研究グループが発表した白髪の発生と特定遺伝子の量との関係。
毛髪の根元にあるたんぱく質FGF(繊維芽細胞増殖因子)をつくる遺伝子の量が減って
はたらきが悪くなると、髪に色をつける色素細胞(メラノサイト)の増殖力や
毛髪細胞の自然死を回避する能力が低下して白髪になるというもので、
花王はこの成果を元に、白髪の予防剤などの開発をめざすという。
白髪がなくなる日はそう遠くないのかもしれない。
だからといってその日まで白髪を放っておくわけにもいかない。
そこで、現在までにわかっている白髪のできるメカニズムと、
その対策をまとめてご紹介しよう。
ヘアサイクルと白髪の原因
| そもそも毛髪はどのようにして色がつくのだろうか。 1本1本の毛髪が生み出される頭皮内の「毛包」と呼ばれる内部には、 毛乳頭という突起があり、毛細血管で運ばれてきた養分をたくわえている。 この毛乳頭を取り囲んでいるのが、毛髪をつくる毛母細胞。 毛母細胞は、毛乳頭から養分を得て、次々に細胞分裂し、毛髪をつくり出していく。 こうしてつくり出された毛髪が少しずつ上に押し上げられ、 頭皮の上に出たのが、いわゆる髪の毛だ。 |
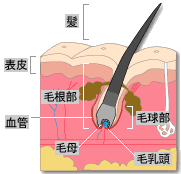
|
| 日本人ならだいたい黒色、世界的にみれば金色あり、茶色あり。 こうした頭髪の色は、毛髪が頭皮内で成長する過程のどこかで、 色素細胞(メラノサイト)がつくり出したメラニン色素が毛髪内に取り込まれることで決まる。 つまり、毛母細胞そのものがつくり出す毛髪は、もともとは白髪なのだ。 それを黒く見せているのは、色素細胞(メラノサイト)がつくり出すメラニン色素のはたらき。 白髪ができるのは、色素細胞(メラノサイト)のはたらきが、 何らかの原因で弱まったり消失したりして、髪を黒くするメラニン色素がつくれなかったためと考えられる。 |
病気によって白髪になる
自然な脱毛の後に、色素細胞(メラノサイト)がスムーズに再配置されない原因とは何だろう。
現在のところ考えられているのは、次の5種類である。
加齢
体の老化によって、当然、色素細胞(メラノサイト)も弱ってくるため。
生活環境
気温などの外的なものはもちろん、食生活や頭皮のケアの状態によっても大きく左右される。
病気
慢性の胃腸疾患やマラリア、貧血症、甲状腺疾患などの病気があると、急に白髪が増えることがある。
また、尋常性白斑(じんじょうせいはくはん)ができるとその部分が白髪になったり、
円形脱毛症が治るときに白髪になるケースも。これらは、病気が完治すると、元の黒髪に戻る場合もある。
ストレス
誰もが納得することだろうが、毛髪とストレスの関係は深い。
「苦労すると白髪が増える」といわれるのも、ウソではない。
ただし、フランス革命の際、
投獄されたマリー・アントワネットの髪が一夜にして真っ白になったという逸話があるが、
そういったことは現在解明されているところではあり得ない。
毛髪は上記の通り、毛先ではなく、毛根から伸びていく。
そして毛髪の色は、頭皮の外へ出たときには、すでに決まっており、
出てから色が変わることは今のところ考えられないのだ。
これらの原因が、ひとつ、あるいは複数重なって白髪が進行すると考えられている。
ここで、遺伝や加齢による白髪だからといって諦めてはいけない。
適切なケアや健やかな生活習慣によって、ある程度は発生を遅らせたり、減らすことはできるのだ。